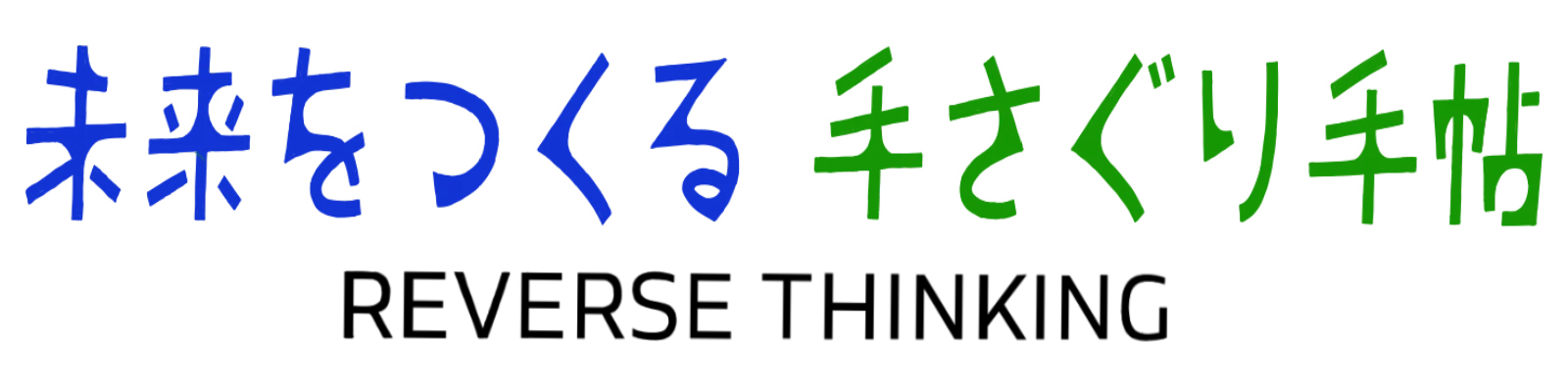「マジックキングダムがファンタジーを現実にしたものだとするなら、エプコットは現実を幻想的にしたものだ。私たちが語る現実の物語、科学と未来、そして文化の物語は、ファンタジーの物語と同じくらい魅力的である可能性がある。」—トニー・バクスター
「The Imagineering Story」第9章 [ 要約 ] :1970年代後半から80年代初頭にかけて、イマジニアリングはウォルト・ディズニーの未完の夢「EPCOT」を新たな形で実現させるという壮大なプロジェクトに取り組みました。当初の「実験的な未来都市」構想から、「未来の世界」と「ワールド・ショーケース」を組み合わせた「永久万博」へと再構想されたEPCOTセンターは、ディズニー史上最大の建設プロジェクトとなりました。マーティ・スカラーとジョン・ヘンチの指揮のもと、新世代のイマジニアたちが加わり、最先端技術を駆使した教育的でありながらもエンターテイニングな体験が創造されました。1982年10月1日にオープンしたEPCOTセンターは、従来の魔法の王国とは一線を画す、現実世界と未来技術をテーマにした革新的なパークとなりました。
第9章「より高い目的」A HIGHER PURPOSE
I. 新しい仲間たち
– マーティ・スカラーの経歴:
– 1955年、21歳のUCLA学生としてディズニーランド・ニュース紙の編集者に
– ウォルトと直接仕事をし、「すべてはストーリーに関するものだった」という教訓を学ぶ
– 1974年にWEDの企画部門副社長に就任
– EPCOTプロジェクトの開始:
– カード・ウォーカー(ディズニー社長)がウォルトの夢を実現させようと主導
– 1973-74年のエネルギー危機や景気後退がディズニーに影響
– プロジェクトのために多くの新人イマジニアが採用される
– 新世代のイマジニアたち:
– ケビン・ラファティ: 元神学生から皿洗い係を経てWEDへ
– トム・モリス: 父親がパイレーツ・オブ・カリビアンの運営者だった若者
– トム・フィッツジェラルド: ディズニーへの情熱から応募、ホーンテッドマンションが特に好き
II. 再構想されたビジョン
– ウォルト・ディズニーのEPCOT構想を変更する必要性:
– 「一人一票」の民主主義社会で、ウォルトの計画した規制された実験都市は法的に実現不可能
– 「ウォルトが達成しようとしたことを支えるパーク」への変更
– 新しいEPCOTの概念:
– 「恒久的な万国博覧会」として再構想
– 文化を紹介する「ワールド・ショーケース」と技術革新を示す「フューチャー・ワールド」の2つのコンセプト
– 最終的に両方を一つのパークに統合する決断
– レジェンダリーなイマジニアたちの関与:
– ハーパー・ゴフやローリー・クランプなど、引退したイマジニアの復帰
– クロード・コーツ、ハービー・ライマン、マーク・デイビスら「ウォルトの世代」との協働
III. EPCOTの世代
– 女性イマジニアの活躍:
– ペギー・ファリス、キム・アーバイン、マギー・エリオット、ケイティ・オルソンなど
– 「私たちをEPCOT世代と呼びましょう」と語るファリス
– ジョン・ヘンチが厳しく指導するカラーデザイン
– クリエイティブな自由と責任:
– 「私たちは続編を作っているのではなく、これまでにないものを作っている」
– 世界中から専門家を招き、新しいアイデアを探求
– 「ウォルトなら何をするか」ではなく「ウォルトは私たちに最善を尽くして欲しいと願うだろう」という姿勢
IV. スペースシップ
– レイ・ブラッドベリの関与:
– 著名SF作家がスペースシップ・アースのナレーション原稿を執筆
– トム・フィッツジェラルドがそれを乗り物用に書き直す
– スペースシップ・アースの開発:
– ジョン・ヘンチのデザインによる世界初の球体型ジオデシック・ドーム
– 高さ165フィート、マジックキングダムの城に匹敵するランドマーク
– 4万年にわたる人類のコミュニケーション史を辿るダークライド
– 各パビリオンの特色:
– 「ワールド・オブ・モーション」: ワード・キンボールの遊び心に満ちた交通の歴史
– 「ユニバース・オブ・エナジー」: エネルギーの歴史と未来を探る
– トニー・バクスターの言葉: 「マジックキングダムがファンタジーを現実にしたなら、EPCOTは現実をファンタスティックにした」
V. 未来が到来
– 革新的なテクノロジーの導入:
– 「ユニバース・オブ・エナジー」屋根の80,000個の太陽電池
– 最新映写技術: 16mmから35mm、35mmから70mmへの拡張
– ドン・アイワークスの機械工房による専用プロジェクター開発
– デジタルオーディオシステムの導入
– ベン・フランクリンが階段を歩く高度なオーディオ・アニマトロニクス
– ランディ・ブライトのイマジニアリング哲学:
– 「視覚的に考える」—言葉は最も重要でないツール
– 「観客の立場に立つ」—常にゲストの視点を想像する
– 「急進的思考」—先入観のない白紙の状態からアイデアを生み出す
– チームワークと協力:
– オーランド・フェランテによる「互いに助け合う」文化の醸成
– 多様な専門家の知識と技術の融合
VI. 世界をEPCOTに持ち込む
– ワールド・ショーケースの開発:
– ハーパー・ゴフの構想: 当初の均一なパビリオンから各国の特色を活かした設計へ
– 「ある国から出て、狭い無人地帯を横切り、異なる音楽や香りや料理の匂いを感じる」体験
– 開園と評価:
– 1982年10月1日、予算12億ドル(当初計画の8億ドルから50%増)でオープン
– 初日約2万人が来場
– カード・ウォーカーの献辞: 「希望をもたらす世界を形作る人間の能力への信念」
– フィグメントの誕生:
– 「イマジネーション」パビリオンの紫色のドラゴン・マスコット
– 元々ディズニーランドの「ディスカバリー・ベイ」向けに開発された「プロフェッサー・マーベル」から進化
– 写真スポンサーのコダック社が気に入り、キャラクターが採用された
この章から読み取れる重要なポイント:
1. ビジョンの適応と進化: ウォルト・ディズニーの元々の構想は法的・実用的に実現不可能だったが、イマジニアたちはその精神を保ちながら新しい形に変換した。イノベーション、未来志向、調和、エコロジーといった根本的な価値観は維持された。
2. 多様性の拡大: EPCOTプロジェクトは、女性イマジニアの活躍の場を広げ、多様な経歴や専門知識を持つ人材を引き寄せた。「EPCOTの世代」は、ディズニーのイマジニアリングに新たな視点と専門性をもたらした。
3. 技術と芸術の融合: EPCOTは前例のない技術的革新(デジタルオーディオ、高度な映写システム、進化したアニマトロニクス)とストーリーテリングの芸術性を融合させた。「現実をファンタスティックにする」というコンセプトは、教育とエンターテイメントの境界を曖昧にした。
4. コラボレーションとスポンサーシップの重要性: 企業スポンサーとの関係は資金調達だけでなく、最先端テクノロジーの情報収集や専門知識へのアクセスという面でも重要だった。プロジェクトの規模は、多様なパートナーシップなしには実現不可能だった。
5. 創造的リスクテイキング: ディズニーランドやマジックキングダムとは全く異なるタイプのパークを作るという決断は、大きな財政的・創造的リスクを伴った。しかし、この「既存のIPに頼らない」戦略は、イマジニアリングの可能性を広げることになった。