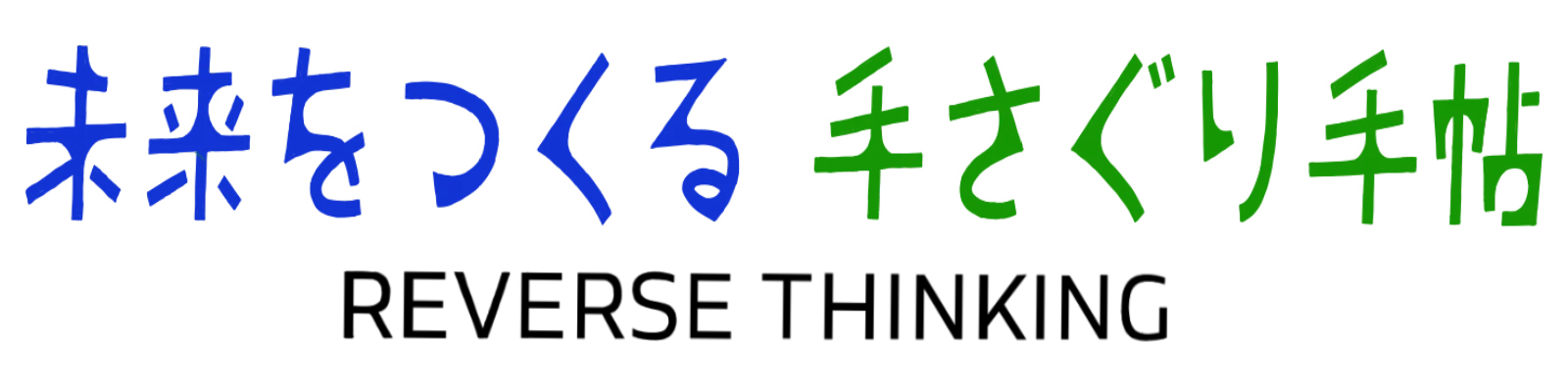『海底二万マイル』〝古典空想科学を現実にする力〟
ジュール・ベルヌ原作、ウォルトによる古典SF実写映画の傑作。執筆されてから八十年も経過しての〝未来〟… ウォルトの「確信ある判断」は、どこにあるのだろうか。〝(少年時代に心躍らせた)奔放奇抜な想像力に充ちたヴェルヌ1〟… 海に潜む潜水艦ノーチラス号、そして乗組員たちの驚くべき海底での光景…、そして秘密の孤島!
〝古典〟空想科学を現実にするウォルトが実写で見せた未来
〝自然と冒険〟記録映画の相次ぐヒットのさなか、「冒険の海」を舞台にウォルトは念願の空想科学映画をつくった。普遍性のあるキャラクター「ノーチラス号」の創出はとてもお見事。… 海の怪物のようにみせる、サメを模した尾ビレ、ワニの皮膚をイメージした表面のたくさんのリベット(鋲)。覗き窓と上部のサーチライトは恐ろしげな目玉を表現している。ウォルトはこのハーパー・ゴフのつくった模型に魅了されて制作を決定したのではないか、とおもえるほどに魅力的。この古典的な意匠の潜水艦を〝原子力〟に置き換え、秘密の孤島に隠しもつという神秘性がいかにもウォルトらしい。
ネモ艦長の信念「やがて原子力を人類が平和のために使う日が来る」と、孤島が軍隊に犯された際、自ら秘密工場を破壊し、潜水艦と共に海中に没してしまう。これはディズニー自身の感性のもつ「革新の先取り」と私には思えた。
想像力と技術力の融合は、ストーリー性を際立たせる好例
ウォルトの創造性と実写映画としての技術力は〝イマジニアリング〟と称することに。… 創造の限界に挑む組織「WEDエンタープライズ」の創設は不可欠だったんですね。
なぜなら、この海底シーンの撮影における革新、水中でのサウンドやミニチュアの演出は、実写においてもアニメ的想像力と工学的技術の融合だった。ウォルトは技術と物語性の両立に確信をもって臨んでいたわけですから。
この例として「ノーチラス号」の内部構造は宮殿のようで、豪華な調度品と珍貴な美術品と、パイプオルガンをも備えて、艦長ネモは超人的な謎の人物として登場している。
視覚的なリアリティーとファンタジーとの共存で、観客を釘付けにしているところはお見事という他はない。
巨大イカとの格闘シーンは、恐怖感を高めるため、荒れ狂う嵐を演出しての撮影に変更させ、制作費も25万ドル以上の追加になったという。ウォルトの卓越した芸術的手腕が際立っていますね。
結論:俯瞰する視点をもち、異分野への好奇心ある行動を試みよう
- 複数分野(物語・意匠・技術)を〝好奇心の目〟で俯瞰できるような視点を持ち、あえて異分野の方との接点を大切にして、育む姿勢が大切。
- 一見〝自分の守備範囲外〟とおもえるような技術や機材に触れてみる。… 発想の幅を広げる行動ですかね。
- 「『海底二万哩 – 制作の意図』ウォルト・ディズニー」より ↩︎