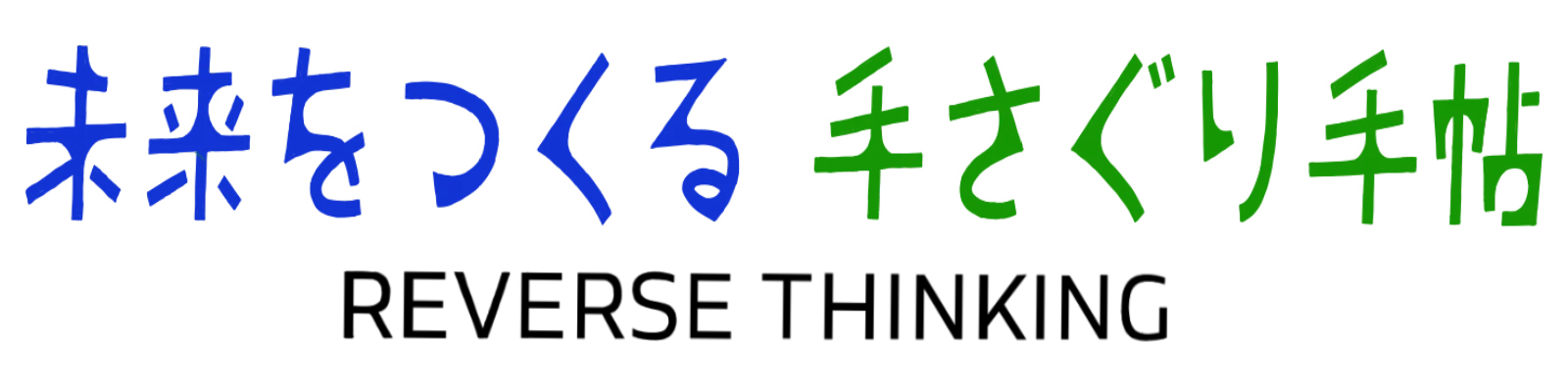「私たちが持っていた感情的な訴求力は、もともと基本的なものでした。大人でも恥ずかしがらずに楽しめるもの…それが私たちの国際的な訴求力につながりました。創業以来、私たちは世界中に多くの観客を抱えてきました。私はそれを常に意識してきました。」—ウォルト・ディズニー
「The Imagineering Story」第10章 [ 要約 ] :1980年代初頭、ウォルト・ディズニー・プロダクションは初の国際的テーマパークとなる東京ディズニーランドの開発に着手しました。カード・ウォーカー会長の初期の躊躇にもかかわらず、オリエンタルランド社(OLC)との提携が実現し、EPCOTセンターと並行して進められたこのプロジェクトは、若いイマジニアたちに大きな責任と成長の機会を与えました。文化的・言語的な課題を乗り越え、マジックキングダムをモデルにしながらも日本独自の要素を取り入れたパークは1983年4月15日に開園。日本文化に深く根付き、驚異的な成功を収めることになります。この経験は、ディズニーの国際展開の可能性を証明するとともに、イマジニアリングの新世代を育成することになりました。
第10章「禅とテーマパーク拡張の芸術」
ZEN AND THE ART OF THEME PARK EXPANSION
I. 日本からの呼び声
– エスモンド・カードン・ウォーカー(カード):
– ウォルト・ディズニーの隣人だった少年時代
– 第二次世界大戦中に海軍に従軍し、真珠湾攻撃後の太平洋で激戦を経験
– 1971年にディズニー社の社長に就任
– オリエンタルランド社の設立と交渉:
– 1960年に浦安の埋め立て地開発のために設立
– 1970年代初頭からディズニーに接触を試みる
– フランク・スタネクの世界展開調査で日本とヨーロッパが有力候補に
– 当初ウォーカーは日本でのプロジェクトに消極的だった
– ディズニーが厳しい条件(OLCが全コスト負担、ディズニーは運営管理権と収益の一定割合を確保)を提示したところ、日本側が即座に受け入れ
– 契約へのプロセス:
– 1974年12月にディズニー幹部が浦安を視察
– スタネクが6ヶ月間の集中的調査を実施し、年間1,700万人の潜在訪問者数を算出
– 1975年9月に東京でプレゼンテーション、同週内に基本合意書に署名
– 1979年4月に最終計画が完成
– 1980年12月3日に神道の清めの儀式とともに起工式
II. 東京世代
– 若いイマジニアたちの東京プロジェクト参加:
– クレイグ・ラッセルやボブ・ワイスなど新卒エンジニアが加わる
– EPCOT中心の会社の中で「小さなチーム」として東京プロジェクトを担当
– 「小回りの利く第二のプロジェクト」として資源制約の中で創意工夫
– 多くの若手が日本に赴任し、2年以上滞在することに
– 文化的交流と信頼構築:
– OLC社長の高橋政知はクオリティに妥協せず、日本のサービス業の新たな基準を目指した
– 100人以上のOLC社員がアナハイムとフロリダで1年間の研修を受ける
– イマジニアたちは深夜にアトラクション内を歩き回り、日本人スタッフに細部を教えた
– 業務外での交流を通じて人間関係と信頼を構築
III. ミート・ザ・ワールド
– マジックキングダムをベースにしながらも必要な変更:
– 言語の問題:「死人に口なし」が直訳で「死人には口がない」になるなど翻訳の難しさ
– メインストリートUSAが「ワールドバザール」に:雨の多い気候に対応するためのガラス屋根
– フロンティアランドが「ウエスタンランド」に改名
– ウエスタンリバー鉄道は一駅のみの設計で日本の鉄道規制を回避
– 日本独自のアトラクション:
– 「エターナルシー」:海洋と人類の関係を日本の視点で描いた映像アトラクション
– 「ミート・ザ・ワールド」:鶴がホストとなり日本の歴史を紹介するオーディオ・アニマトロニクスショー
– シャーマン兄弟が作曲したテーマ曲、クロード・コーツがデザイン、ブレイン・ギブソンが人形の頭部を彫刻
– 第二次世界大戦は「嵐と稲妻」の映像で簡潔に表現
– 開園と成功:
– 1983年4月15日に開園、カード・ウォーカーとOLC高橋社長がテープカット
– 開園前に300万枚のチケットが売れ、開園後1年以内に1,000万人が来場
– 4年以内に6億5,000万ドルの初期投資を回収
– 「日本人女性の人生で最も楽しい経験」として多数が挙げるほどの人気に
– 日本の多くの遊園地がディズニーランドの圧倒的な存在感に閉園を決断
– 「外国旅行」の代替として、「アメリカ文化の最高の部分」を体験する場所に
– リピーター率85%という驚異的な顧客ロイヤルティを獲得
– 世代を超えて継承される「文化的ランドマーク」に
この章から読み取れる重要なポイント:
1. 文化的適応と普遍性のバランス: 東京ディズニーランドの成功は、ディズニーの基本的な魅力が文化を超えて普遍的であることを証明すると同時に、言語や文化的文脈に合わせた慎重な調整の重要性も示した。ウォルト・ディズニーの「良い歌はどんな言語でも通用する」という信念が実証された。
2. リスク分散型ビジネスモデルの開拓: ディズニー社にとって初めての「所有せず、ライセンス供与する」モデルを確立。財政的リスクを最小化しながら国際展開する方法として、この東京での経験は後の海外パーク開発の基盤となった。
3. 若手人材の成長と継承: EPCOTと並行して進んだ東京プロジェクトは、資源制約の中で若いイマジニアたちに大きな責任と創造性の機会を与え、次世代のイマジニアリングリーダーを育成した。「東京世代」のイマジニアたちは後にディズニーの国際展開を牽引することになる。
4. 歴史的和解と文化橋渡し: 第二次世界大戦で敵対した米国と日本が、エンターテイメントを通じて新たな友好関係を築いた象徴的事例。「ミート・ザ・ワールド」での戦争の扱いに見られるように、難しい歴史的トピックを尊厳をもって処理する方法が模索された。
5. 細部への徹底的なこだわり: 言語翻訳から運営トレーニングまで、ディズニー品質を維持するための細部へのこだわりが、日本文化の完璧主義とサービス重視の価値観と共鳴し、パークの成功に不可欠だった。年間1,000万人以上の来場者という予測不可能な成功は、このクオリティへの徹底したこだわりから生まれた。