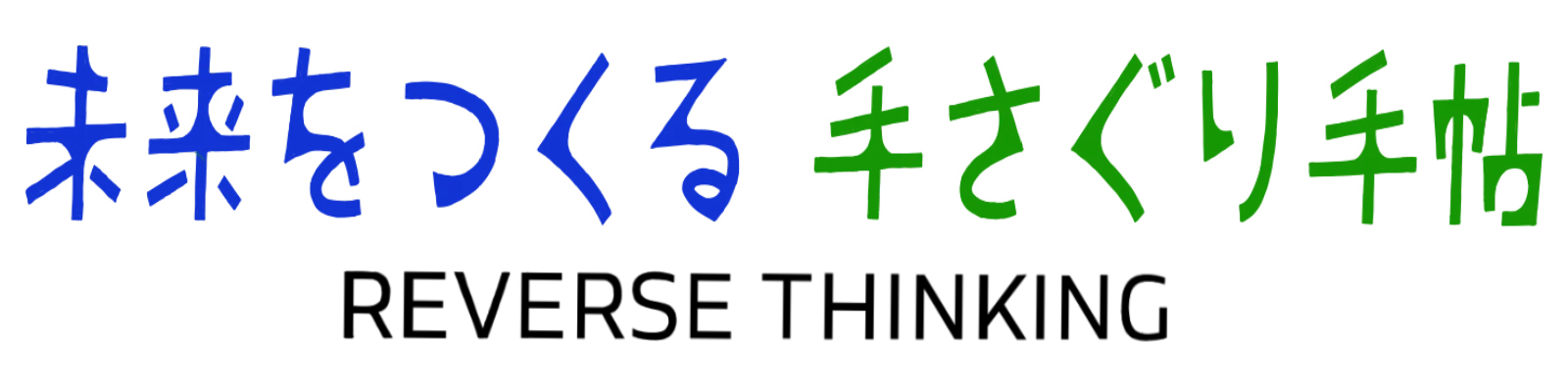[ウォルト・ディズニー]は、あなたが昨日何をしたかには全く興味がありませんでした。彼が興味を持ったのは、あなたが今日、そして明日何をするかだけでした。なぜなら、彼は常に前進し、新しいことに挑戦し、私たちに挑戦し続けていたからです。それは刺激的なことでした…想像してみてください。自分がうまくやれるかどうか、期待に応えられるかどうか、全く分からなかったとしても、彼はあなたを信じていたのです。だからあなたはやり遂げたのです。
—マーティ・スクラー
「The Imagineering Story」第3章 [ 要約 ] :ディズニーランドは単なる遊園地ではなく、三次元で体験できる「映画」でした。ウォルト・ディズニーとイマジニアたちは、パークの設計に映画製作の手法を適用し、「強制遠近法」や「視覚的マグネット」を活用して没入感のある環境を創造しました。開園後も「プラッシング」(継続的な改良)の哲学に基づき、アトラクションを次々と追加・拡張。1959年には「マッターホルン・ボブスレー」「潜水艦航海」「モノレール」という3つの革新的アトラクションを同時に開業させ、1963年には初のフル・オーディオ・アニマトロニクスショー「魅惑のチキルーム」を完成させました。これらのプロジェクトはイマジニアリングの技術的革新と芸術的表現を融合させ、ディズニーランドを常に進化する「生きた」場所として確立したのです。
第3章「革新と刷新」INNOVATE AND RENOVATE
I. 映画の手法
– ディズニーランドは三次元の映画という概念:
– 「ショットが編集され、アート・ディレクションが施された」エクスペリエンス
– メインストリートUSAは「タイトルカード」として機能し、城が「物語の主要舞台」を示す
– 土地から土地への移行は「映画のディゾルブ」のように機能
– ジョン・ヘンチの説明:
– 「時間を通じて得られる体験」
– 「映画や本と同じように展開する」
– 「音楽のセグエのような」土地間の移行
– 映画の技法を建築に適用:
– メインストリートUSAの建物の「強制遠近法」
– 上階が縮小されることで錯覚を生み出す設計
– 歩道と道路の理想的な比率(1:2:1)の追求
– ウォルトの「ウィニー」(視覚的マグネット)概念:
– 眠れる森の美女の城が中心的な「ウィニー」
– 各ランドには独自の視覚的引力点を配置
– 来場者を誘導し、方向感覚を与える役割
– ハブ・システムの重要性:
– パリやワシントンDCの放射状設計からインスピレーション
– 疲れた来場者が休息できる中心地点
– 各ランドへ均等にアクセスできる設計
II. パークのプラッシング、パート1
– ウォルト・ディズニーのパーク訪問:
– 定期的に来場者と交流し、アトラクションを体験
– イマジニアたちにも同様の体験を求めた
– 「プラッシング」の哲学:
– 「完成することのない、生きて呼吸する存在」としてのパーク
– 常に改良し、追加する姿勢
– 「昨日やったことではなく、今日と明日何をするかに興味がある」
– 初期の追加アトラクション:
– 「ロケット・トゥ・ザ・ムーン」や「アストロ・ジェット」などのトゥモローランド・アトラクション
– 「トム・ソーヤー島」(1956年):子供の探検エリア
– 「ストーリーブック・ランド運河ボート」:モデルショップの技術の見せ場
– 「スカイウェイ」(1956年):空中ケーブルカー
– チケット制度の進化(A〜Cチケットの導入)
III. 上り坂、水中、空中
– マッターホルン・ボブスレーの開発:
– ディック・ヌニスによる「スリルライド」の提案
– ウォルトがスイス映画撮影中にマッターホルン山に着想
– ボブ・ガーによる革新的なパイプ式ローラーコースターの設計
– 複雑な計算と物理学の応用
– スカイウェイを貫通させる設計上の課題
– 潜水艦航海:
– 「ファントム・ボート」の失敗から生まれた新アトラクション
– 「沈む」錯覚を作り出す設計
– 人魚のパフォーマーによる生きた要素の追加
– モノレールシステム:
– ウォルトの長年の夢
– ドイツのALWEG社との提携
– ボブ・ガーによる未来的デザイン
– 「空中のハイウェイ」として宣伝された都市交通の未来像
– 1959年6月14日の盛大なお披露目:
– リチャード・ニクソン副大統領の参加
– ABCテレビ特番「コダック・プレゼンツ・ディズニーランド59」
– 新たな「Eチケット」の導入
IV. 新たな頂点
– 「Eチケット」の文化的影響:
– 最上級の興奮を表す表現として一般文化に普及
– NASAの宇宙飛行士サリー・ライドの「間違いなくEチケットだった」発言
– セレブリティの関与:
– ニクソン副大統領と人魚の出会い
– シエラクラブのマッターホルン登頂デモンストレーション
V. パークのプラッシング、パート2
– マーク・デイビスのWEDへの移籍:
– アニメーション部門での「シャンテクレール」企画の失敗
– ウォルトに「ディズニーランドに足りないものは何か」と聞かれ「ユーモア」と回答
– ジャングル・クルーズの改良:
– ユーモアある場面の追加(サファリ隊の木登りシーンなど)
– より多くのオーディオ・アニマトロニクス動物の導入
– 「魅惑のチキルーム」の誕生:
– 当初はレストランとして構想
– ジョン・ヘンチの「鳥かごの中の鳥」アイデアから発展
– ローリー・クランプの運動彫刻と木製の神々
– WEDの総力を結集したプロジェクト
– シャーマン兄弟による「チキ・チキ・チキ・ルーム」の作曲
– 1963年6月23日の開業と大成功
– マーティ・スカラーの評価:
– 「全ての才能が一つのアイデアに集中した」プロジェクト
– 「繰り返し何度も上演できる」エンターテイメントの基礎を確立
– 後の「イッツ・ア・スモールワールド」、「パイレーツ・オブ・カリビアン」、「ホーンテッド・マンション」の土台となった
VI. 新しい拠点
– WEDエンタープライズの新拠点:
– 1961年8月にグレンデールのグランド・セントラル・ビジネスパークに移転
– 「パンケーキハウス」と愛称される本社ビル
– モデルショップの中心的役割:
– ハリエット・バーンズをはじめとする職人たち
– コラボレーションと多様な技術の融合
– 「WEDの心臓部」としての機能
– ウォルト・ディズニーの遊び場:
– 「私はここで働くのではなく、遊びに来るんだ」というウォルトの言葉
– 「仕事から離れた工房」としてのWED
– 「誰にも許可を求めずにやりたいことができる場所」
この章から読み取れる重要なポイント:
1. 映画的アプローチの応用: ディズニーランドの成功は、映画製作の技法(フレーミング、シーケンシング、ディゾルブ、強制遠近法など)を物理的空間に適用したことにあります。このアプローチにより、一貫したストーリーテリングと没入感のある環境が実現しました。
2. 継続的革新の哲学: ウォルト・ディズニーの「完成することのない、生きて呼吸する存在」という考え方は、単に施設を維持するだけでなく、常に改良し、新しいものを追加する姿勢を確立しました。これは「プラッシング」と呼ばれ、ディズニーパークの持続的な魅力の基盤となっています。
3. 技術的革新と芸術的表現の融合: マッターホルン(世界初のパイプ式ローラーコースター)、モノレール(西半球初の日常運行システム)、魅惑のチキルーム(初の完全なオーディオ・アニマトロニクスショー)は、技術の限界を押し広げながらも、芸術的な物語体験を提供しました。
4. 多様な才能の協働: 異なる背景と専門知識を持つアーティストたちを一つの組織に集結させることで、革新的なアイデアと解決策が生まれました。アニメーターから彫刻家、エンジニア、景観設計者まで、多様な才能の融合がイマジニアリングの強みとなりました。
5. ユーザー体験を中心とした設計: ウォルトとイマジニアたちが定期的にパークを訪れ、一般ゲストと同じ体験をしたことは、ユーザー中心の設計アプローチを確立しました。この実践的なフィードバックループが、パークの継続的な改善に不可欠でした。