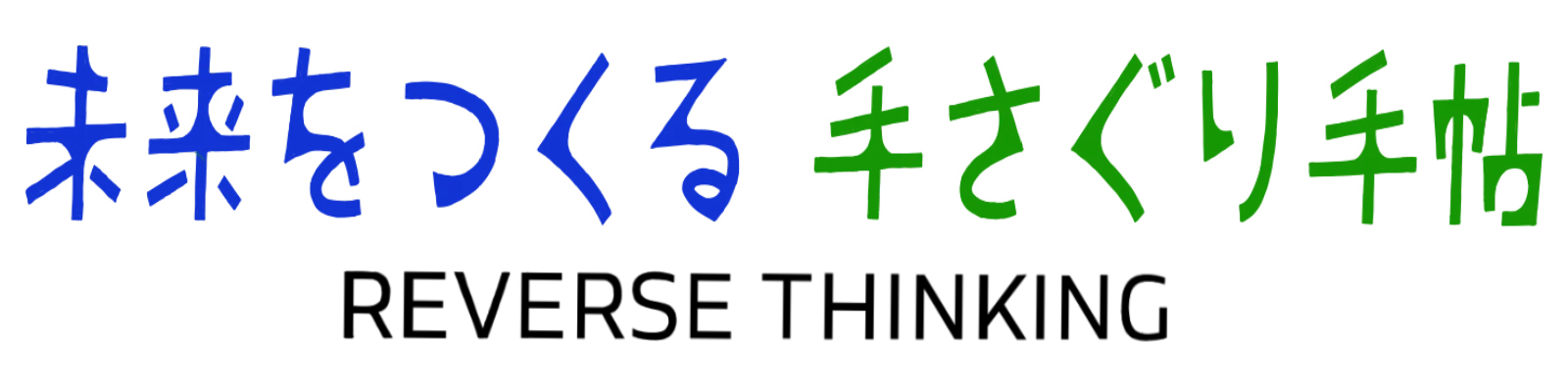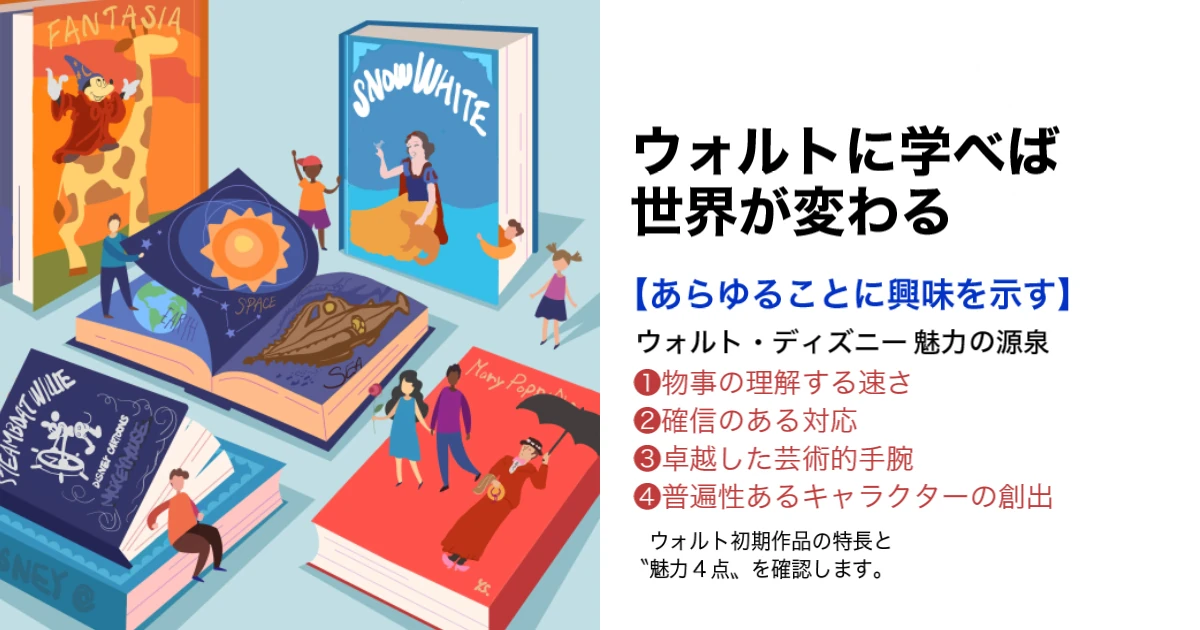ミッキーの魅力はウォルトそのもの。…生き生きした遊び心、創意や機知に富んだ楽しいキャラ。 ウォルト・E・ディズニー自身〝生きることの素晴らしさ〟を感じきる生涯だったからと言えるでしょう。彼の最大の特徴の一つは〝あらゆることに興味を示すところだ1〟と証言している。そして、〝ウォルトの仕事ぶりには、無駄というものが一切なかった2。〟ここでは彼の人となりを、初期の作品から垣間見てみたい。
ディズニーは全力で、生きる喜びを創出した
ここに一冊の本『ディズニーの芸術』(1977年発刊 クリストファー・フィンチ著)。この中に、ウォルト・ディズニーの〝人となり〟が記述されています。
まとめると、以下の4点が彼を特徴づけていると伺えます。
①物事の理解する速さ
[理解力]
30年代半ばにスタジオ入りしたジャック・カディングは彼の人となりを、こう見ている「ウォルトは実際の年齢以上に円熟して見えました。…それは彼が非常に繊細な神経の持ち主であったからだと思います。他人の考えを把握することや気持ちを理解するのがとても速いのです。」
②確信のある対応
[対応力]
ディズニー社のベテランのディック・ヒューマーはウォルトがいかに明快な答えを出す男であるかを痛感して、こう言っている。「彼はいつも答えをもっていました。常に問題の核心に直行し、問題の原因を引っぱり出しました。まったく嫌になりますよ。誰だって自分の頭を引っ叩いて言うでしょう。『どうして彼にわかって自分にはわからないんだ?』って」
③卓越した芸術的手腕
[感性]
ルネ・クレールは言う。「ウォルト・ディズニーはプロデューサーであり、監督であり、そのうえ物語の進行、音楽に至るまで気を配っている。その芸術的手腕は最高である。」
④普遍性あるキャラクターの創出
[創造性]
ミッキーマウスの普遍性について…当時のヘラルド紙の特派員は記事を書いている「私は世界中駆け回ったが、どこへ行ってもミッキーマウスと一緒だった。太平洋諸国、日本、中国、その他の小さな国々においてさえも、ミッキーにお目にかかった」「ミッキーをはじめとするディズニーのキャラクターが高く評価されている以上、ディズニー社がついに数百万ドルを売り上げる(当時)企業になったのは驚くに値しない。」
この4点に留意し、作品に照らし合わせながら紐解くことで、魅力ある〝ビジョンつくり〟のヒントが見出せるのではないか。〝ウォルトの凄さは、映画の質にこだわりながら、スタッフの参加意識を鼓舞することにあった。そして形式ばらないウォルトの性格はスタジオに一種の仲間意識を育ませる。〟… その一端をのぞいてみたい。
ウォルトは感性を駆使し、珠玉の5作品を生み出した
1. 『蒸気船ウィリー』(1928)
- 初の商業的に成功した音声付きアニメーション。ミッキーマウスのデビュー作であり、ウォルト自身が声を演じた。アニメーションにおける音と動きの同期という革新が業界に衝撃を与えた。
2. 『白雪姫』(1937)
- 世界初の長編カラーアニメーション映画。スタジオに莫大なリスクを課したが、世界的ヒットを記録。アニメーションが“芸術”や“映画”として認知される契機となった。
3. 『ファンタジア』(1940)
- クラシック音楽とアニメーションを融合させた実験的な芸術作品。当時としては革新的な「ステレオサウンド(Fantasound)」技術を導入し、音響の表現力を飛躍的に向上させた。商業的には苦戦したが、芸術性と先進性が再評価されている。
4. 『海底二万マイル』(1954)
- 初の本格的実写SF映画。ウォルトがアニメ以外の分野へ挑戦し、特撮・機械技術・物語性の高さでディズニー作品の幅を広げた。潜水艦ノーチラス号のデザインは今もレジェンドとされる。
5. 『メリー・ポピンズ』(1964)
- 実写とアニメのハイブリッド表現の到達点。ジュリー・アンドリュースの名演と共に、音楽、ストーリーテリング、技術の融合が高く評価された。アカデミー賞5部門受賞で、ディズニー映画の質の高さを印象づけた。
以上の5作品を取り上げてみました。