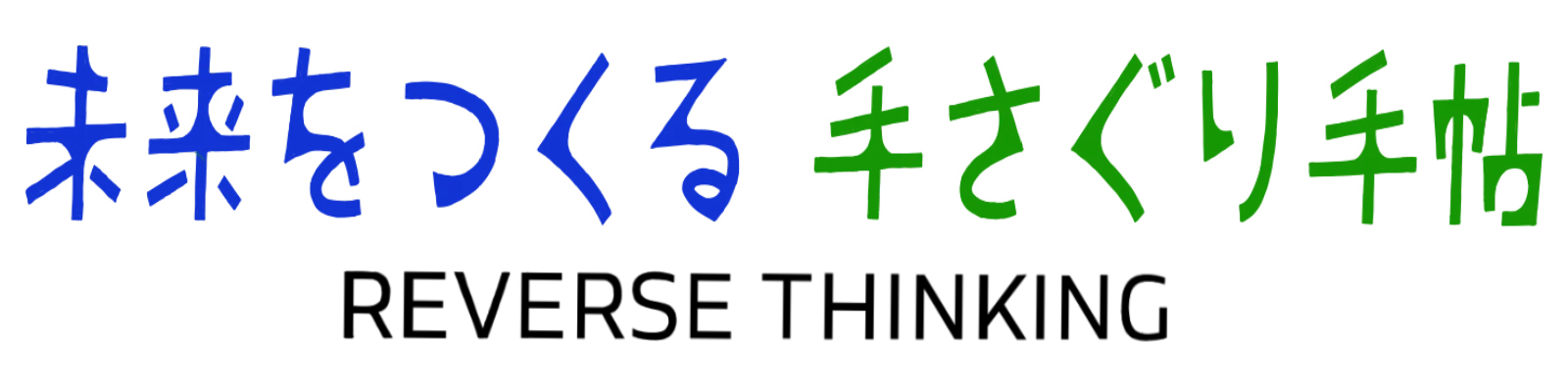『ファンタジア』〝音楽を観る〟という挑戦
ウォルトはミッキーマウスの行く末を案じ、1938年ウォルトは短編『魔法使いの弟子』をアニメ化、音楽の曲を使ってミッキーの再起を図るが、… レストランでの、ある交響楽団の有名指揮者からの申し出に〝長編コンサート映画〟へと発展。クラシック音楽をビジュアルで表現するというウォルトの〝芸術性への挑戦〟が開始された。
〝音楽をアニメーションで表現する〟 ディズニーの芸術革命
クラシック音楽とアニメーションを融合したこの作品は、技術・芸術・音響設計における総合芸術の到達点だった。
音楽とアニメの結晶『ファンタジア』とは?
ウォルトはデュカス交響詩「魔法使いの弟子」を使って、ミッキー主演の豪華短編を作りたいと、高名な指揮者ストコフスキーに話すと、その音楽の指揮をしようと申し出た。彼はディズニーのファンだったのだ。… この野心的な短編は二人の共同作業で、数曲で構成される長編映画へと発展した。
当初『Concert Feature(コンサート物語)』と呼ばれていた、このプロジェクトは「音楽と映像による壮大なファンタジー」とウォルトの言葉から『ファンタジア』というタイトルに、この指揮者から提案された。
なぜウォルトは、芸術性に賭けたのか
それは、ミッキーの影が薄くなったと感じていたことです。
初期のミッキーは小説家のジョン・アップダイクが言う初期のミッキーは「アメリカそのものであり、元気で人がよく、創意に富み、回復力があり、気さくで勇敢」だった。」しかし、〝親しみやすいものになり、ありふれて取るに足らないものになっていったのだ。〟
アニメーターのフリッツ・フリーレングは「アニメの目新しさがなくなると、あとにはなにも残らなかった。ミッキーマウスは無価値なものになってしまった」と語っている。
ミッキーマウスの大ファンだった指揮者のレオポルド・ストコフスキーは痛感していて(?)〝クラシック音楽をアニメーションに仕立てるという夢の構想を〟をウォルトに熱心に語りはじめたことに端を欲します。
… ウォルトは〝目に映った印象というものを常に大切にしていた「子どもの頃コンサートに行ったけど、今でも目に浮かぶよ、オーケストラが音合わせをしているところ…。指揮者が登場して演奏が始まる、… バイオリンの弓が上がったり下がったりする…。」〟(同上)
あの、シルエットでミッキーマウスが指揮台に駆け上がり、指揮者ストコフスキーを称え握手しているシーンを後世に映像で残し、価値を高めたかったのかもしれないですね。!?
… でも、真実は以下のスタッフ会議での意気込みある言葉にあると察します。「音楽が意味するものをスクリーン上で観れば、音楽が理解できるようになる。音楽には映像と類似点がある。『トッカータとフーガ』に耳を貸さない人々を取りこむことがわたしたちの目的だ」
常識を越えた〝表現〟の冒険
「わたしは型にはまりたくない、スタッフを型にはまらせたくない」とウォルトはロサンゼルス・タイムズ(1941.2.21)「もし精神的に芸術的に成長をやめた時には、それは衰弱、死を意味する」〝「成長しなければならない。最大限の努力が必要だ…」が、ウォルトの生涯を通じての信念だった。…高度な芸術の力を借りて、粗雑で幼稚とされる大衆文化から漫画を昇華させようとした。…〟(『創造と狂気 ウォルト・ディズニー 』ニール・ゲイブラー著)
ウォルトは映画館についても新しい試みを考えていた。〝特殊なメガネを利用して立体画像が鑑賞でき〟〝館内に花の香りを漂わせる〟こともストコフスキーに提案、さらには〝スピーカーを館内の前後左右に設置し〟立体的な効果を狙った。ウォルトは「ファンタサウンド」と名付けた。
まさしくウォルトの第六感をもとに、〝五感を活用しての感性の創出〟を願うウォルトの冒険といえましょう。
あなた自身の〝芸術的手腕〟を育てるには
- 自身の専門領域とは違う「芸術表現」の理解へも関心の領域をひろげ、感性の多層化を意識、新たな自分を見出す試み(例:音楽×ビジュアル×人生ストーリーの創出)
- ビジョンの構築にあたり、人生観をビジュアル面から逆算思考で組み立て直してみる
まとめ
「色と音と動きの世界における終わりなき発見の旅である私たちの仕事…そのなかで『ファンタジア』は最もエキサイティングな冒険だ」ウォルト・ディズニー