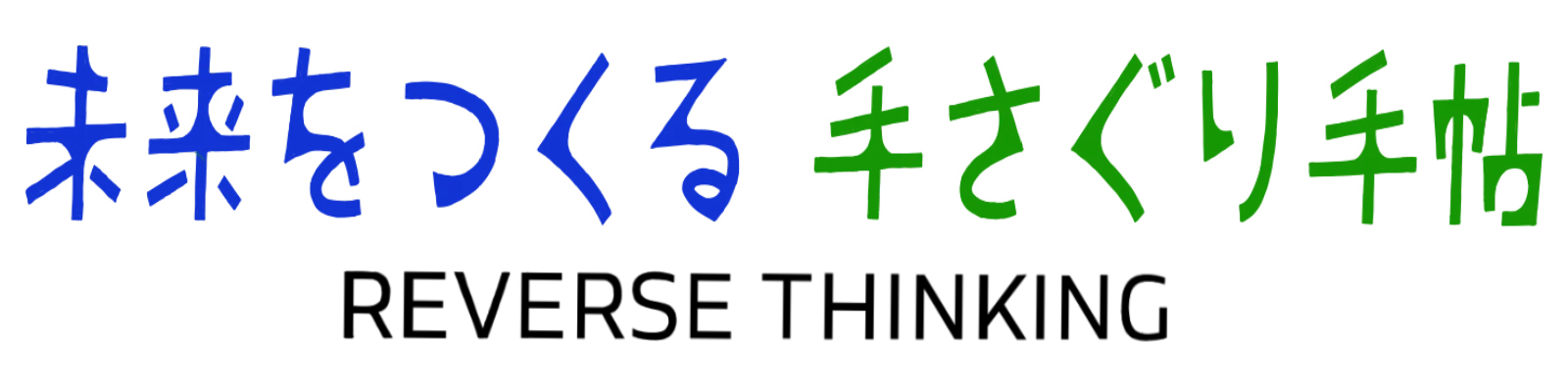ウォルトは喜劇俳優キートンの『蒸気船』をパロディに、ミッキー2作目の映画を企画。その際、当時話題の初トーキー映画『ジャズ・シンガー』と〝漫画〟の二本立て上映が評判とのウワサを耳にする。するとウォルトが「それでいこう!」と叫んだ。… まさにウォルトの〝時代を理解する速さ〟がこの作品の革新性を生んだ。
音と動きの融合 – ウォルト・ディズニーの直感、理解力が未来をひらく
革命の瞬間に『蒸気船ウィリー』誕生
音とアニメの動きを融合させるという技術的ブレイクスルーは、まさに彼の時代の先を読む〝直感と理解力〟によるものだった。前年の1928年初頭、NYで話題となる初トーキー映画『ジャズ・シンガー』から、わずか数ヶ月でアニメ『蒸気船ウィリー』を制作、試写し、サウンドをシンクロさせてみせ、… ウォルトたちは拍手喝采!アンコールの拍手が鳴りやまなかったという。ウォルトは「まさにこれだ!」と、興奮は収まらなかった。
音とアニメーションとが融合できた、本当の理由
裏切りに会い、〝オズワルド〟そして制作スタッフたちを失い、手元の資金も枯渇しようとしていた。そんななかで開かれた歴史的なブレーンストーミングのなかで生まれたのでした。
いわゆるトーキーと呼ばれた有声映画の登場で、ハリウッドは混乱状態に陥り、大手は独立系のスタジオにこの〝サウンドシステム〟を使わせまいと妨害。ウォルトは入手しやすいニューヨーク!と判断し、あり金をかき集め一人、フィルムを小脇に楽譜と共にニューヨークに向かう。1928年9月のことである。ウォルトの目には、映画界がフランス革命のさなかにあるように映ったという。… 〝音の革命〟に混乱した映画会社は、性能の良い〝録音システム〟を求め、奪い合いが展開されていた。
だが、NYの録音技術に関する専門家たちの話にはウォルトは納得できなかった。〝音とアクションはピタリと一致〟だから、音はフィルム上に一緒に録音しなければと確信していくのでした。… 映画界の幹部たちが〝トーキーは得体の知れないものでしかなかった〟のに対し、ウォルトは映画の音というものがもつ将来にますます可能性を強めた。
「弟のウォルトと私は、1923年に一緒に事業を始めた。私が思うに、実際のところウォルトは、本当の天才だった。創造的で、決意が固く、ひたむきで、活力に満ちていた」ロイ・O・ディズニー
「彼の最大の特徴の一つは〝ありとあらゆることに興味を示すところだ〟」ハリソン・エレンショウ(『過去から今へ:ディズニースタジオにて』〈Disney +〉)
まずは、以下の文面から読み取ってみましょう(『ウォルト・ディズニー – 創造と冒険の生涯 』)
〝ウォルトとアブはキートンの喜劇を拝借し、『蒸気船ウィリー』を作ることにした。前半のアクションは、昔からよくボードビルで流されていた『蒸気船ビル』の曲に合わせ、後半は『わらの中の七面鳥』に合わせるという趣向である。〈しかし、一体全体、どうやって音とアクションを合わせればいいんだろう …〉ウォルトは考えこんだ。彼は音楽に関しては、ずぶの素人であった。〟
晩年、ウォルトはインタビューに答え、こう語っている。
〝想像力っていうやつは直観的なものだ。これは生まれつきの才能だと思うけど、でも、その後の発達が必要です。私の場合、小さい頃、ボードビルをいろいろ見にいって勉強になりました。カンザスシティにいたころ、…僕らは一週間に三回もショーを見物したもんです。… 私自身、もともと政治漫画を描こうと思ってましたが、カンザスシティのフィルム・アドという会社で漫画映画に触れたのが方向転換のきっかけになりました。… でも私は漫画を描くだけでは満足できなくて、カメラマンの仕事を観察しながら露出はいくらとか、どうしてそういうふうに撮影するのか、などと質問しました。最初は何を訊いても答えてくれなかったカメラマンが、そのうち何でも教えてくれるようになって、私に撮影までさせてくれたんです。こうやって私は、いろいろ学んだというわけです。… 〟
ここで、読み取れることは…物事を絶えず〝この世に生の不可思議さを体感、〝正しい目で捉えていた〟ということでしょう。
革新性は、ウォルトの吸収力と即応力の賜物だった
ショービジネス界の実業家はウォルトに言う。「結局は、観客の評判をとることが先決なんだ。」…1928年11月18日『蒸気船ウィリー』は封切られ、ウォルトが描いていたとおりの大ヒットとなる。『ニューヨーク・タイムズ』紙は「この映画は実に楽しい、独創的な作品である。」芸能誌『バラエティ』は「はじめから終わりまで、音とアクションがピッタリ合った素晴らしい出来栄え。…特別の賛辞を贈りたい、…すべての映画劇場に自信をもって推薦する」と褒めた。ウォルトは毎晩、客席の後ろに立って、新鮮な笑いの波に聞き入ったという(『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯』著者:ボブ・トマス)
新しいものへの「即理解、即応」が創造の突破口となる
いま、私たちにできる「即理解、即応」の実践法
- 日常の中で目にした〝新しい技術、表現〟に対し、即座に「自分の文脈で応用するなら?」と問う習慣をもつ。
- 他業界の最先端を毎週チェックし、アイデア「転用ノート」を作成する。